古美術商との付き合い方
ある程度、目が肥えてきたら、骨董市だけでは物足りなくなってきます。
なぜなら、やはり、良い物は、古美術商の下に集まっているからです。
ただし、古美術商は、如何せん、敷居が高い!
土日は、閉まっている上に、閉鎖的。お客なのに、なぜかこちらが、遠慮しないといけない。そんな不思議な世界です。 しかし、うまく古美術商との付き合いを学べば、収集家としてレベルアップを図れるでしょう。
目次
- どうやって古美術商を選ぶか?
- 古美術商との付き合い方
- 古美術商との付き合い方(メリット編)
- 古美術商におけるマナー
- 伝説の古美術商に関して
- 超一流店と言われる古美術商
どうやって古美術商を選ぶか?
まず大事なのは、自分が何を収集しているのかを伝えること!
古美術商に、「何をお探しですか?」と聞かれて、「分かりません。」だと、話になりません。
「まだ、始めたばかりですが、これこれこういう物が好きなんです。」と伝えておけば、きちんと対応してくれるはずです。
選ぶ基準としては、
自分の収集している物を専門に扱っている店。
店に飾っている商品が、自分の感覚に合うと、お店の人とも合います。
後は、店主の人柄をよく見て、自分と合うか判断しましょう。
骨董選びも、古美術商選びも目利きです。是非、間違わないようにしてください。
古美術商との付き合い方
信頼できそうな古美術商を見つけたら、まずは、安くてもいいので、物を買ってみましょう。
安くても、一度、何かを買ってくれたお客であれば、古美術商の中で、あなたへの見方が変わります。長きに渡るお付き合いへの先行投資と思いましょう。
ただ、まだまだ、駆け出しのあなたにとっては、少しのお金でも、買うという行為が怖いものです。
その際は、将来、よりグレードが高い物が欲しくなった時に下取りしてくれるかどうか聞いてみましょう。 古美術商にもよりますが、人によっては、10万円で購入したものを後日、7~8割掛けで買い取ってくれ、その店で買う20万円の買い物に当てることができます。
その後は、忘れられないように、時折、顔を出し、人間関係を少しずつ築いておきましょう。
古美術商との付き合い方(メリット編)
古美術商と付き合うようになれば、非常に大きなメリットがあります。
本やネットでは、決して手に入れることができない情報や知識を習得できます。
新しい商品が手に入ると色々と見せてくれたり、業界の裏話を聞かせてくれたり、骨董の見分け方など長年培った古美術商の知識を教えてもらうことができるのです。
また、時には安くしてもらえたり、分割購入出来たりなど、いろいろな相談に乗ってくれるようになります。 さらに、仲良くなれば、あなたが探していたものが入荷すると、優先的に電話がかかってきて教えてくれます。
古美術商におけるマナー
私が、気づいた気をつけないといけないこと。
- 商品を触る時は、一言声を掛けましょう。
- 安くしてもらいために、商品について、難癖をつけるのは止めましょう。
- 一度、購入したものを、時間をおかず、下取りを希望するのは、あまり好かれません。
- 小さなお店だと、場合によっては、お客さんと商談中の時があります。そういう時は、邪魔せず、時間を置いて訪ねましょう。(事前に、電話で予約しておくのも良いです。)
- 他店で買った骨董品の真贋を尋ねるのは、止めましょう。後で、他店とトラブルになるので、はっきりした回答を嫌がります。
伝説の古美術商に関して
偉大な収集家のもとには、常に古美術商の存在がありました。 日本を代表する伝説の古美術商は、こちらです。
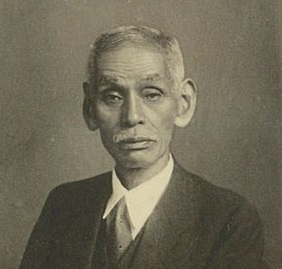 山中定次郎(1866年-1936年) |
明治、大正時代の古美術商で、日本を代表する山中商会の初代社長。積極的に、海外に日本の古美術を紹介し、英国、米国など海外に支店を出し、
海外の名だたる貴族、実業家と親交を持つ。フランスの宝石商アンリ・ベーベルの浮世絵コレクションを松方幸次郎に斡旋し、数千点の浮世絵が松方コレクションに加わった立役者も、この山中氏。
今だに、山中商会の扱った古美術品は、畏敬の念を持たれて扱われる。 【参考図書】「ハウス・オブ・ヤマナカ―東洋の至宝を欧米に売った美術商」 |
|---|---|
廣田不孤斎(1897年- 1973年) |
大正から昭和期にかけて活動した日本の古美術商・蒐集であり、東京日本橋の古美術店「壺中居」の共同創業者。中国・朝鮮・日本の陶磁を収集し、鑑賞陶器の世界の第一線で活躍した古美術商。第2次世界大戦の終戦まで、しばしば中国を訪れて古陶磁を請来し、岩崎小弥太・細川護立・横河民輔といった大蒐集家に納める。
【参考図書】「骨董裏おもて」 廣田不孤斎 (著) |
坂本吾郎(1923年 - 2016年) | 日本の古美術商。古美術店・不言堂の創設者。1972年のロンドンでクリスティーズのオークションにおいて、中国・元時代の「青花釉裏紅大壺」を約1億7600万円で落札。この金額は、当時の東洋陶磁において世界最高額であり、中国古磁器の評価が高めた。
数々のオークションに参加し、世界的な名品を日本にもたらす。
【参考図書】「ひと声千両―おどろ木 桃の木「私の履歴書」 坂本吾郎(著) |

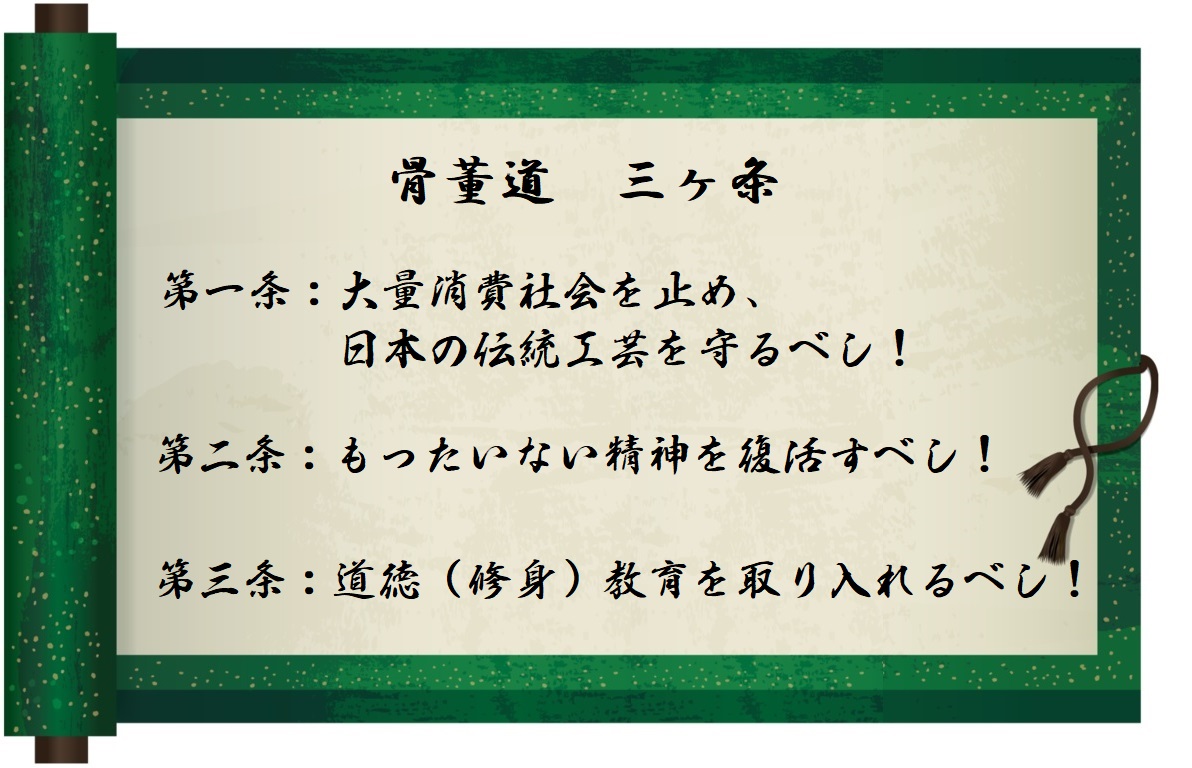





.jpg)
